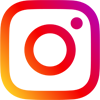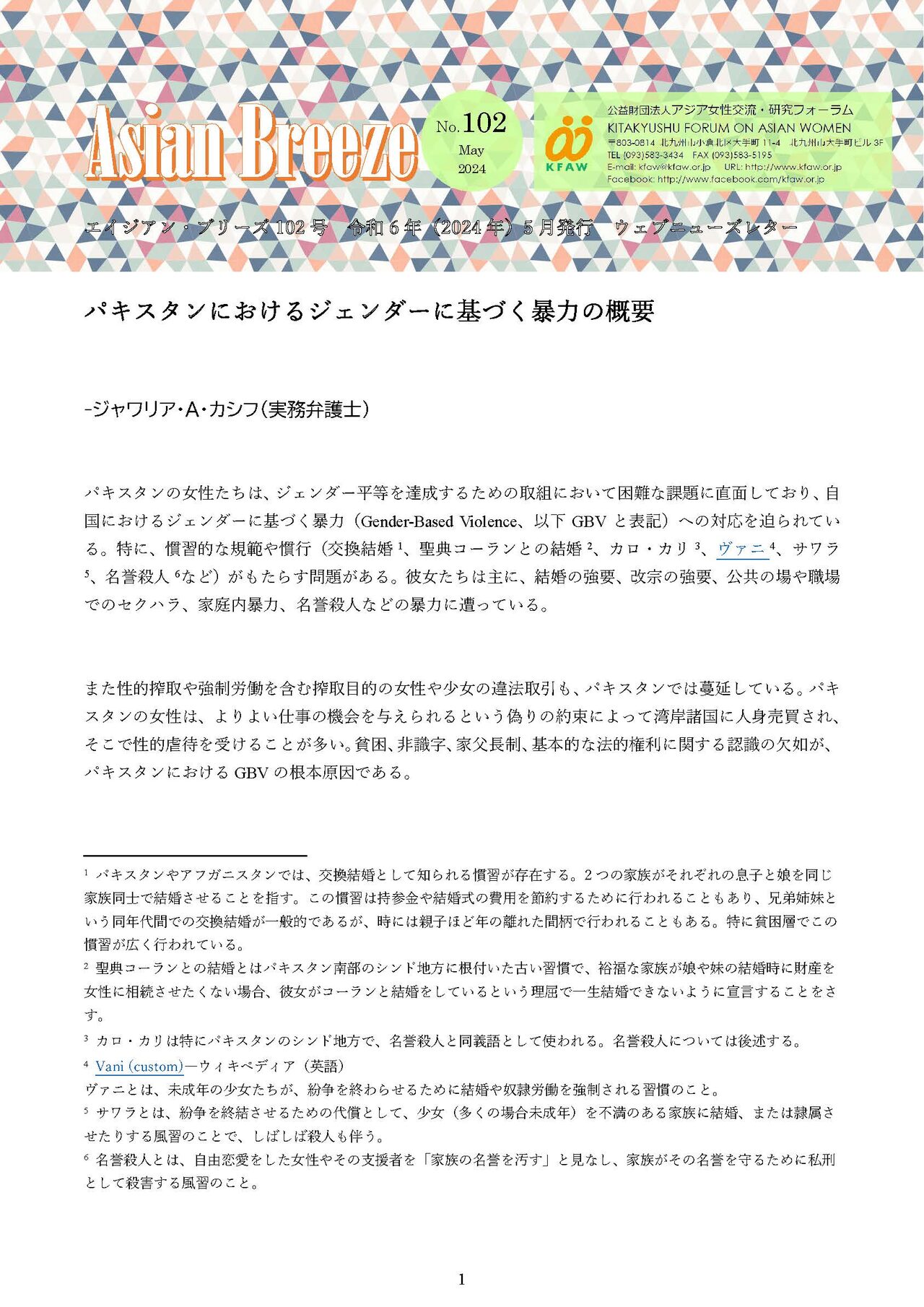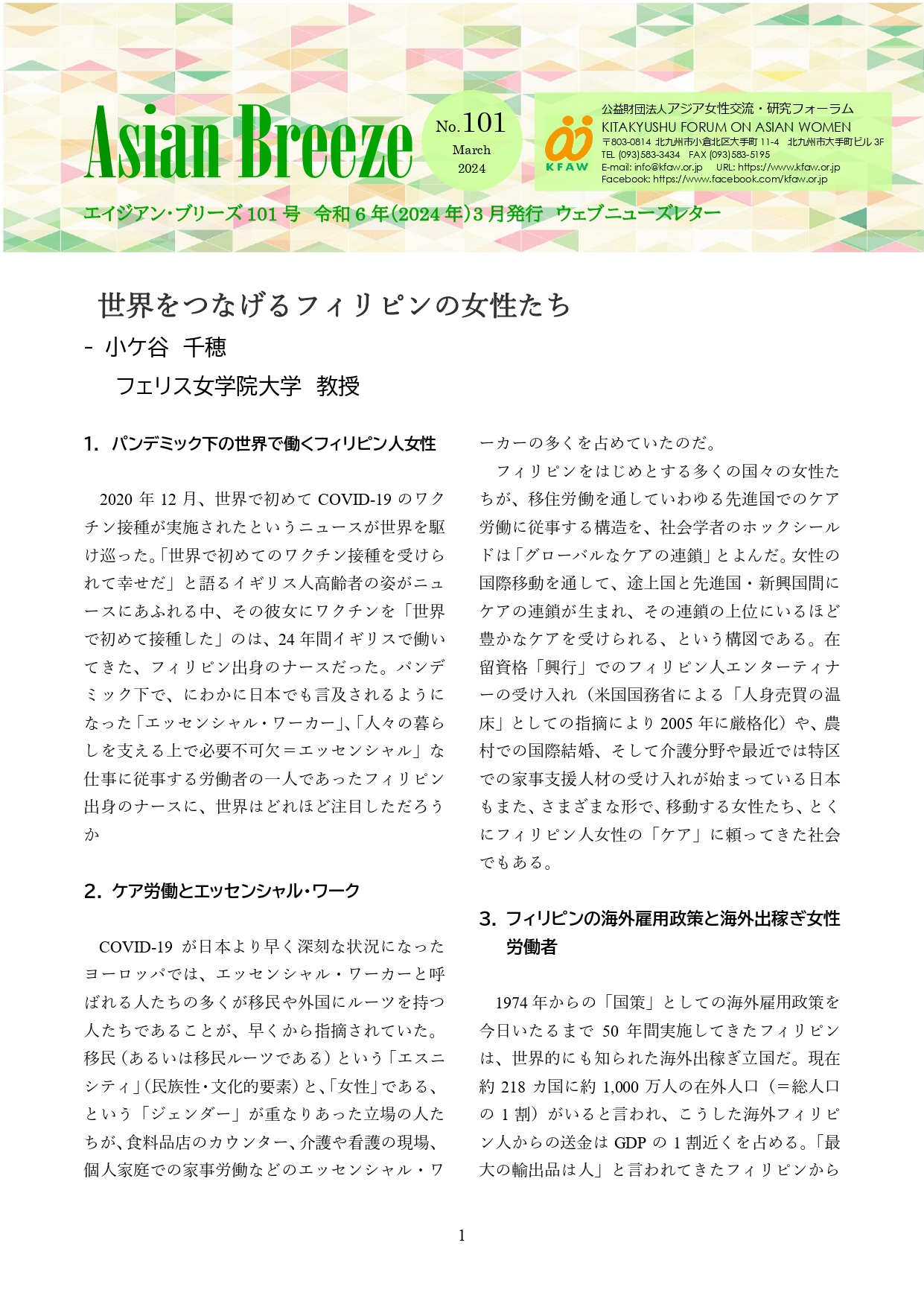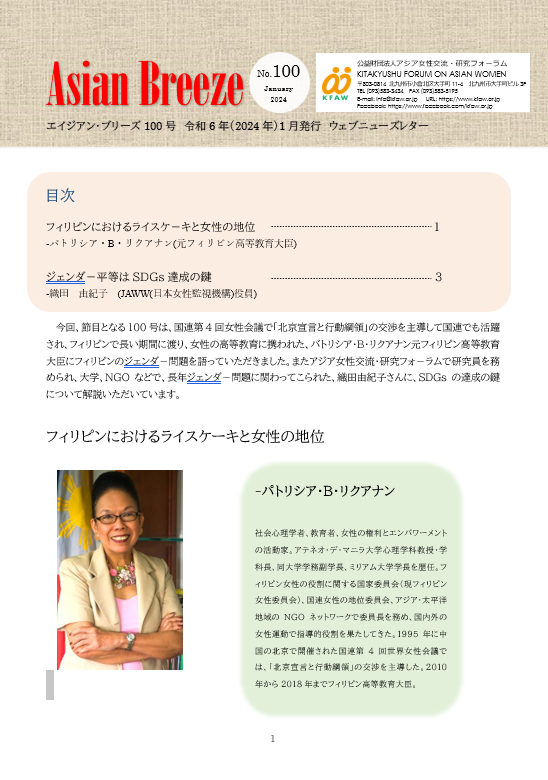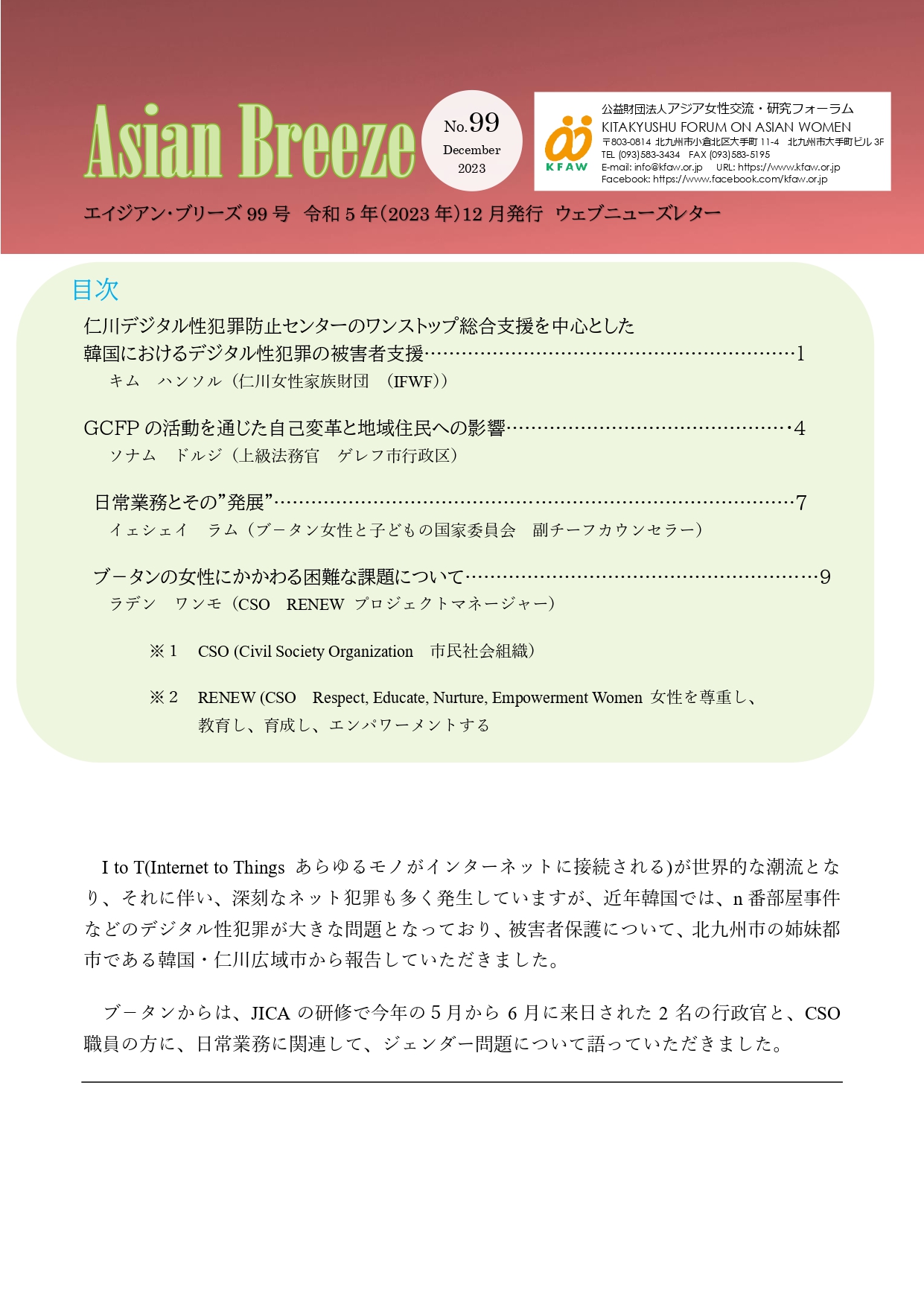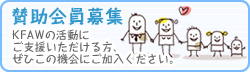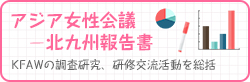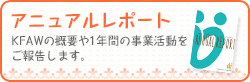Asian Breeze
『Asian Breeze』は、(公財)アジア女性交流・研究フォ-ラム(KFAW)がアジアの女性関連情報を日本語と英語で発信しているニュ-ズレタ-です。
ジェンダ-平等、女性・少女のエンパワ-メント、SDGs、環境問題など、最新のトピックスを幅広く取り上げており、「アジアの女性の今」を見ることが出来ます。是非ご覧下さい。
Asian Breeze 105号(ウェブニュ-スレタ-)
Asian Breeze 104号(ウェブニュ-スレタ-)
Asian Breeze 103号(ウェブニュ-スレタ-)
Asian Breeze 102号(ウェブニュ-スレタ-)
Asian Breeze 102号
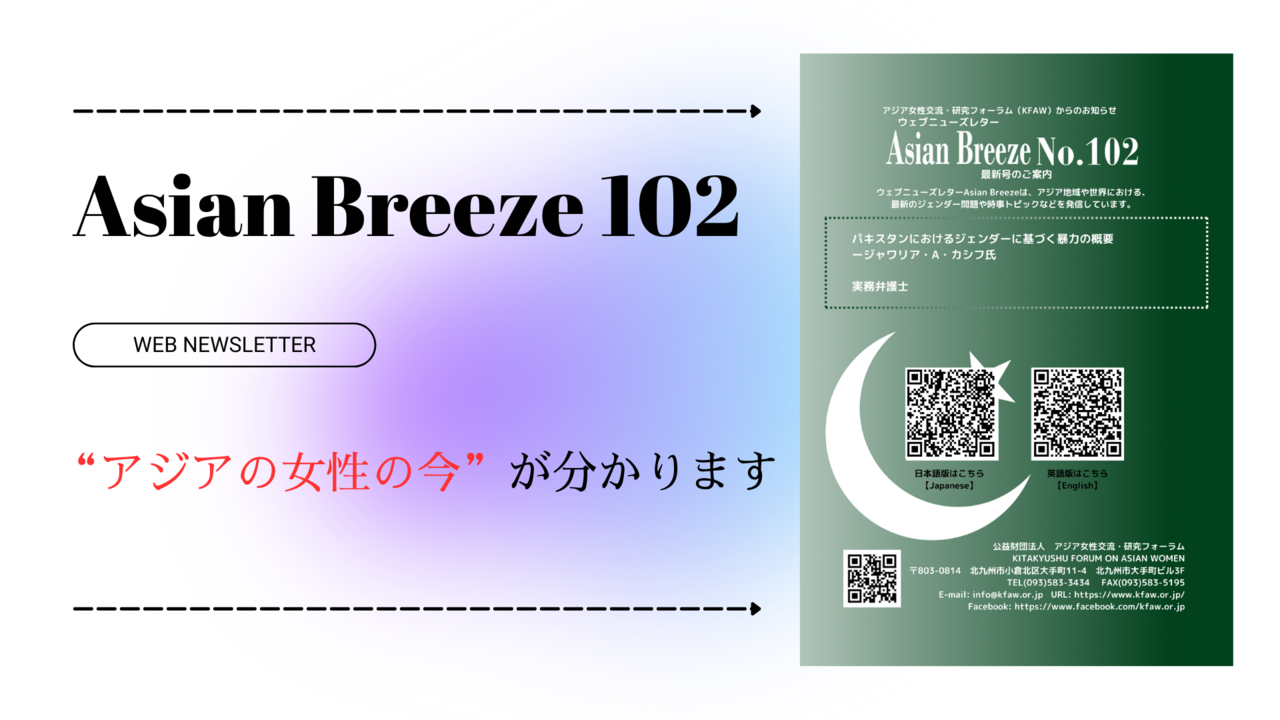
パキスタンにおけるジェンダーに基づく暴力の概要
-ジャワリア・A・カシフ(実務弁護士)
パキスタンの女性たちは、ジェンダー平等を達成するための取組において困難な課題に直面しており、自国におけるジェンダーに基づく暴力(Gender-Based Violence、以下GBVと表記)への対応を迫られている。特に、慣習的な規範や慣行(交換結婚 、聖典コーランとの結婚2、カロ・カリ3、ヴァニ4、サワラ5、名誉殺人6など)がもたらす問題がある。彼女たちは主に、結婚の強要、改宗の強要、公共の場や職場でのセクハラ、家庭内暴力、名誉殺人などの暴力に遭っている。
また性的搾取や強制労働を含む搾取目的の女性や少女の違法取引も、パキスタンでは蔓延している。パキスタンの女性は、よりよい仕事の機会を与えられるという偽りの約束によって湾岸諸国に人身売買され、そこで性的虐待を受けることが多い。貧困、非識字、家父長制、基本的な法的権利に関する認識の欠如が、パキスタンにおけるGBVの根本原因である。
1 パキスタンやアフガニスタンでは、交換結婚として知られる慣習が存在する。2つの家族がそれぞれの息子と娘を同じ家族同士で結婚させることを指す。この慣習は持参金や結婚式の費用を節約するために行われることもあり、兄弟姉妹という同年代間での交換結婚が一般的であるが、時には親子ほど年の離れた間柄で行われることもある。特に貧困層でこの慣習が広く行われている。
2 聖典コーランとの結婚とはパキスタン南部のシンド地方に根付いた古い習慣で、裕福な家族が娘や妹の結婚時に財産を女性に相続させたくない場合、彼女がコーランと結婚をしているという理屈で一生結婚できないように宣言することをさす。
3 カロ・カリは特にパキスタンのシンド地方で、名誉殺人と同義語として使われる。名誉殺人については後述する。
4 Vani (custom)―ウィキペディア(英語)
ヴァニとは、未成年の少女たちが、紛争を終わらせるために結婚や奴隷労働を強制される習慣のこと。
5 サワラとは、紛争を終結させるための代償として、少女(多くの場合未成年)を不満のある家族に結婚、または隷属させたりする風習のことで、しばしば殺人も伴う。
6 名誉殺人とは、自由恋愛をした女性やその支援者を「家族の名誉を汚す」と見なし、家族がその名誉を守るために私刑として殺害する風習のこと。
-パキスタンで最近報告されたGBV事件は以下のとおり:
– 2024年3月29日、男性が再婚を拒否した妻7を殺害。
– 2024年2月26日、ある女性がアラビア語のプリントの入った服装8をしていたためにハラスメントを受けた。警察が介入し、暴徒から女性を救出。
– 2024年3月17日から18日にかけての夜被害者9は兄と父親から近親相姦を受け、殺害された。最初の報告によると、彼女は妊娠しており、彼らは彼女を殺害する計画を立てていた。
– 2024年2月25日、12歳の家政婦が拷問10され殺害された。
– 2023年11月29日、ソーシャルメディア上の写真に10代の娘が写っていたため、男が家族の長老の指示で10代の娘を殺害。11
– 2023年9月27日、パンジャブ州で誘拐された女性がレイプ12後に殺害された。
– 2023年3月、ラホールでキリスト教の未亡人が改宗を拒否したためにレイプされ殺害された。
憲法による保護や国際的な取り決めにもかかわらず、様々な資料はGBVが様々な形で全国的に存在することを示している。ロイター財団が2022年に発表した報告書によれば、パキスタンは、女性にとって全体的に危険な国として上位6位、家庭内暴力ではワースト5位に位置しており、国際的に見て女性の安全が確保されていない国である。
国家人権委員会(NCHR)は2023年3月8日、政策概要13を発表し、パキスタンにおける3年間のGBVの事例が約6万3000件に上ると報告した。特に懸念されるのは、Covid-19の蔓延を緩和するために実施されたロックダウンに端を発する2020年前半に始まったGBVの急増である。ロックダウンが実施された後、最初の半年で約4,000件のGBVが報告されたが、その後の2年半では、半年あたり平均10,500件のGBVが報告された。このGBVの急激な増加は、ロックダウンによる家族の時間の増加とDV事件の悪化との間に強い相関関係があることを浮き彫りにしている。これらのケースの80%は家庭内暴力に関連するものであり、約47%は既婚女性が性的虐待を受ける家庭内レイプに関連するものだった。このデータは報告されたケースに基づくもので、実際の件数はさらに多いことが懸念される。
パキスタンのパンジャブ州で1,000人の女性を対象に行われた調査によると、既婚女性の70%から90%が、配偶者からの虐待や家庭内暴力を経験している。配偶者やその他の男性親族による女性への暴力は、パキスタンで最も蔓延している暴力の形態である。また早期の児童婚は、配偶者による暴力の主な原因のひとつである。未成年の少女は結婚生活の責任を負うほど成熟しておらず、そのために配偶者やその他の親族から暴力を受けている。暴力は肉体的なものだけでなく、心理的なもの、言葉によるもの、経済的なものなど様々である。このような恐ろしい行為を引き起こす原因はいくつもある。その最たるものが、パキスタンにおいて家父長制が敷かれ、男性優位が広く見られるという事実である。
最近発表された『パンジャブ・ジェンダー・平等・レポート2022』14は、女性に対する暴力事件が驚くべき頻度で発生していることを露わにしている。報告書では、パンジャブ州単独の女性に対する暴力事件を取り上げている。しかし、国内の他の地域でも、同様に女性に対する暴力事件が発生している。パンジャブ警察監察官事務所が2022年に収集したデータ15によると、パンジャブ州では34,854件もの女性に対する暴力事件が報告されており、最も多い犯罪は誘拐であった。また、この1年間に1,024人の女性が殺害された。殺害された女性のうち、395人が家庭内暴力で、176人が名誉殺人16、453人がその他の動機で命を落とした。パキスタンの他の州における有罪や無罪の割合を示す具体的な数字はないが、パンジャブ州で報告されたGBV事件のうち、有罪判決を受けたのはわずか4%で、96%は無罪判決に終わっている。
すべての性別、特に女性が暴力、虐待、差別、搾取から保護される暴力のない社会を実現するために、パキスタン政府、NGO、権利擁護団体が協力し、その努力の結果、優れた連邦法、州法17が制定され、その実施のための強力な制度も施行されている。パンジャブ・パキスタンにおける法整備の好例として、夫、兄弟姉妹、養子、親戚、家庭内雇用主による家庭内、性的、心理的、経済的虐待、ストーカー行為、サイバー犯罪から女性を守ることを目的とした「パンジャブ対暴力女性保護法」(The Punjab Protection of Women against Violence (Amended) Act 202218)の施行が挙げられる。2022年のPPWAV法改正後、パンジャブ州女性保護局のもとに設立されたパンジャブ・パキスタンの地区女性保護センターは、ひとつ屋根の下でGBVサバイバーにサービスを提供している。
2022年の「職場におけるセクシャル・ハラスメント防止法」(The Protection against Harassment of Women at the Workplace (Amendment) Act, 202219 )も非常に良い法律である。これは職場の定義を拡大し、正規の職場と非正規の職場の両方を包含するものである。この新しい法律で保護されるのは、特に職場での暴力やハラスメントのリスクが高い家事労働者も含まれている。この法律においてハラスメントの定義が拡大され、「性別を理由とする差別(性的であるかどうかは問わない)」も含まれる。これまでに寄せられたハラスメントに対する訴えのデータは、詳細な報告書20に記載されている。
トランスジェンダーをハラスメントや差別から保護し、救済し権利の擁護を図り、福祉を増進するために、「2018年トランスジェンダー(人権保護)法」(The Transgender Persons (protection of rights) act 201821)がパキスタンの国会で可決された。「反レイプ(調査および裁判)法(2021年22」(Anti-Rape (Investigation and Trial) Act 2021 )第13条1項は、GBVの被害者の医学的・法的診察のための2本指処女検査を明示的に禁止している。GBV法廷でのオンカメラ審理 も、GBVサバイバーが事件について適切に語ることができるように行われている。
パキスタンは、最近の積極的な法整備の後、ジェンダーに無関心な状態から、正式な制度によっていくらかジェンダーを考慮する状態へと移行した。パキスタンの女性たちは、自分たちの権利についてゆっくりと少しずつ理解し、そのために闘い、声を上げている。しかし、女性の安全を確保するまでの道のりは遠く、パキスタンにおけるGBVを根絶するための総合的な取り組みが急務である。
7再婚を断った女性を男性が殺害―海外メディア(英語)
8冒とくの疑いで暴徒に囲まれた女性を警官が救出―海外メディア(英語)
9男性が妹を殺害―海外メディア(英語)
1012歳の家政婦が殺害される―海外メディア(英語)
11パキスタンの父親と3人の親族を名誉殺人の疑いで逮捕―海外メディア(英語)
12拉致された女性が襲われた後に殺害される―海外メディア(英語)
13DOMESTIC VIOLENCE POLICY BRIEF p.7―英語資料
14Research and Publication―英語資料
15 Punjab Records 10,365 Cases Of Violence Against Women In Just Four Months―英語資料(英語)
16HONOUR KILLING REPORTED CASES (2011-2022)―英語資料
17 List of Federal and Provincial Pro-Women Laws―英語資料
18Aiming to Achieve Violence Free Society for Women―英語資料
19The Protection against Harassment of Women at the Workplace―英語資料
20 OFFICE OF THE OMBUDSPERSON GOVERNMENT OF THE PUNJAB―英語資料
21The Transgender Persons (protection of rights) act 2018―英語資料
22The section 13(1) of Anti-Rape (Investigation and Trial)Act 2021―英語資料
23別室でカメラを介して審理を行うこと。日本ではビデオリンク方式に当たる。
著者について
ジャワリア・A・カシフ
GBV被害者との法律啓発セッション

女性の権利、権利の否定に関する法的処罰について男性も感化され、家族の中で女性を平等に扱うよう指導される

公共の場でのハラスメントや、職場でのハラスメントに関する女性への啓発セッション

大学生を対象にした、家族法や憲法の基本的権利に関する啓発セッション

パキスタンにおけるトランスジェンダーの権利に関するセッションで、トランスジェンダーが国家データベース登録局 ( National Database and Registration Authority)とID登録に関する問題について議論している

今回のWeb版Asian Breezeはいかがでしたか。ぜひご意見、ご感想をお聞かせください。
Eメール→info@kfaw.or.jp
Asian Breeze 101号(ウェブニュ-スレタ-)
Asian Breeze 101号
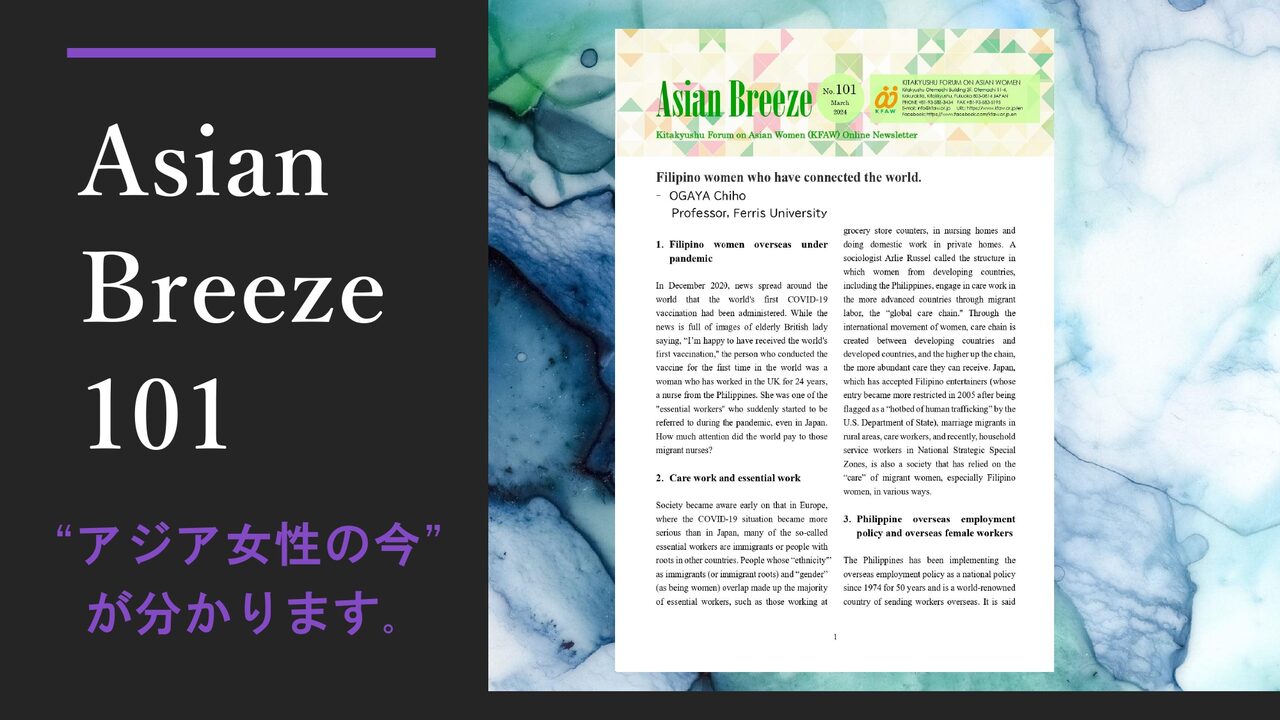
世界をつなげるフィリピンの女性たち
– 小ケ谷 千穂
フェリス女学院大学 教授
1.パンデミック下の世界で働くフィリピン人女性
2020年12月、世界で初めてCOVID-19のワクチン接種が実施されたというニュースが世界を駆け巡った。「世界で初めてのワクチン接種を受けられて幸せだ」と語るイギリス人高齢者の姿がニュースにあふれる中、その彼女にワクチンを「世界で初めて接種した」のは、24年間イギリスで働いてきた、フィリピン出身のナースだった。パンデミック下で、にわかに日本でも言及されるようになった「エッセンシャル・ワーカー」、「人々の暮らしを支える上で必要不可欠=エッセンシャル」な仕事に従事する労働者の一人であったフィリピン出身のナースに、世界はどれほど注目しただろうか
2.ケア労働とエッセンシャル・ワーク
OVID-19が日本より早く深刻な状況になったヨーロッパでは、エッセンシャル・ワーカーと呼ばれる人たちの多くが移民や外国にルーツを持つ人たちであることが、早くから指摘されていた。移民(あるいは移民ルーツである)という「エスニシティ」(民族性・文化的要素)と、「女性」である、という「ジェンダー」が重なりあった立場の人たちが、食料品店のカウンター、介護や看護の現場、個人家庭での家事労働などのエッセンシャル・ワーカーの多くを占めていたのだ。
フィリピンをはじめとする多くの国々の女性たちが、移住労働を通していわゆる先進国でのケア労働に従事する構造を、社会学者のホックシールドは「グローバルなケアの連鎖」とよんだ。女性の国際移動を通して、途上国と先進国・新興国間にケアの連鎖が生まれ、その連鎖の上位にいるほど豊かなケアを受けられる、という構図である。在留資格「興行」でのフィリピン人エンターティナーの受け入れ(米国国務省による「人身売買の温床」としての指摘により2005年に厳格化)や、農村での国際結婚、そして介護分野や最近では特区での家事支援人材の受け入れが始まっている日本もまた、さまざまな形で、移動する女性たち、とくにフィリピン人女性の「ケア」に頼ってきた社会でもある。
3.フィリピンの海外雇用政策と海外出稼ぎ女性労働者
出稼ぎ立国だ。現在約218カ国に約1,000万人の在外人口(=総人口の1割)がいると言われ、こうした海外フィリピン人からの送金はGDPの1割近くを占める。「最大の輸出品は人」と言われてきたフィリピンからは、パンデミック後も年間約200万人以上の労働者が海外に出ているが、その半分近くはケア労働に従事する女性たちである。彼女たちの家事労働・介護労働者としての就労は、常に危険にさらされ、賃金や労働条件も守られにくい職場であり続けてきた。1995年に「移住労働者のマグナ・カルタ」(共和国法8042号)を制定したフィリピンにあって、常に海外労働者の権利保護という課題を政府に突き付けてきたのは、こうした海外で働く女性労働者たちの存在であった。送り出し国として、家事労働者の最低賃金を決めたり、資格を付与したりとさまざまな施策を試みてきたフィリピン政府ではあるが、依然として海外で働く女性たちの権利侵害は絶えず、また、フィリピンの多くの大衆映画が今日まで描いてきたように、家族が送金に依存し続ける中、「母」や「娘」たちへのプレッシャーは増すばかりだ。
4.BPO産業とフィリピンの女性たち-フィリピン国内にいて、世界をつなぐ
2000年代以降のフィリピンで、海外出稼ぎに次ぐ経済の柱となってきたのが、IT-BPO産業である。代表的なのは、多国籍企業のコールセンターで昼夜を問わず働く大卒の女性たちだ。エアコンの効いたオフィスや、パンデミック下でも在宅勤務が可能など、「英語を使った収入のよい仕事」として人気を集めているコールセンターの仕事も、実際には夜勤の多さや不安定就労と無縁ではない。そこでもまたフィリピンの女性たちは、世界中の消費者と企業とを「つなぐ」役割を、英語能力と、ある種のケア労働(「カスタマー・ケア」)を通して担っている。韓国人や日本人の若者向けのフィリピンの英語学校で講師を務めるフィリピン人女性たちもまた、同様にケア労働的な役割を期待されながら、世界を「つないで」いる。
振り返れば、フィリピンの女性たちは、以前からずっとグローバル経済を影で支えてきた。1970年代からの輸出向けの外資系工場で働く「器用な指先」とされた女性たち。セックスツーリズムの中で外国人男性から消費され搾取されてきた女性たち。こうした女性たちと、メトロマニラのコールセンターで、そして日本の高齢者施設で現在働いているフィリピン人女性たちは、つながっている。時代を超えて、グローバル経済を、世界を「つないできた」女性たちなのだ。
5「つながれた」世界は、彼女たちをリスペクトできているのか
歴史的にスペインやアメリカの植民地支配下にあったことにより築かれてきた英語力とホスピタリティの上に、「明るいフィリピン人」「大家族でケアに向いている」という言説が生まれてきた。そのことが、皮肉にも、低賃金でグローバルな「ケアの下請け」とも言えるような役割をフィリピン人女性たちが担うという世界的な構図を生み出してきた。彼女たちのさまざまなケアを通して「つながれてきた世界」は、果たしてその「ケア労働」の価値をきちんと評価できているのだろうか。「女性向け」の仕事とされやすい低賃金、重労働、長時間のケアやサービス職種。それは、「外国人だから」やってくれるだろうとされる低賃金、重労働、長時間職種でもある。パンデミックを契機に、こうした移住女性によるケア労働が、社会にとっていかに「エッセンシャル=欠くことのできないもの」であるかが、あらためて浮き彫りになった中、ケア労働の価値をどう考えるか、という課題は、日本を含むすべての世界に共通する課題である。
日本で暮らすフィリピン出身の女性たちの多くは、ミックス・ルーツの若者たちの母親でもある。さまざまな分野で活躍する、多様性を体現する若者たちを日々育ててきたのは、彼女たちだ。こうした母親たちの貢献も含めて、わたしたちは、フィリピン出身の女性たち、そして広く移住女性たちの存在を、リスペクトできているのだろうか。

小ヶ谷 千穂(おがや ちほ)
フェリス女学院大学文学部コミュニケーション学科・教授
横浜市男女共同参画審議会委員(会長)
川崎市多文化共生社会推進協議会委員
1997年一橋大学社会学部卒業。2003年一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得退学。横浜国立大学教育人間科学部准教授を経て、現職。専門は国際社会学、ジェンダーと国際移動。主にフィリピンからの人の移動を中心に、香港やシンガポールなどに家事労働者として働きに行く女性たちの組織活動や、出身家族との関係について研究。その後、ヨーロッパや北米で暮らすフィリピン人移住者のネットワークや、国境を越えて移動する子どもたち、「ダブル」「ハーフ」と呼ばれてきた若者たちの語りをもとにしたアイデンティティ研究を進めている。
フィリピン留学中の2000年より、日本から帰国した移住女性とその子どもであるJFC(Japanese Filipino Children)のエンパワーメントに取り組むDAWN(Development Action for Women Network)の活動に参加。JFC劇団「あけぼの」日本公演や各種DAWNの活動を日本側からサポートするDAWN-Japanの一員として活動。大学教員になってからは、日本の学生とJFCとの交流活動にも取り組んでおり、最近ではDAWNをはじめとするJFCと母親たちの支援組織の歴史とその役割についても研究している。
主な著書に『移動を生きる:フィリピン移住女性と複数のモビリティ』(有信堂高文社2016年)、 『国際社会学』(有斐閣・共編著2015年)、『家事労働の国際社会学』(人文書院・共著2020年)。最近の論文に、「移動から考える“ホーム”-画一的な“ステイ・ホーム”言説を乗り越えるために」(『現代思想』Vol.48-10特集:コロナと暮らし―対策の現場から、青土社2020年)、「日比間の人の移動における支援組織の役割:移住女性とJFCの経験に着目して」(共著・フェリス女学院大学文学部紀要No.55、2020年)、「共生を学び捨てる―多様性の実践に向けて」(岩淵功一編『多様性との対話-ダイバーシティ推進が見えなくするもの』青弓社2021年)など。
今回のWeb版Asian Breezeはいかがでしたか。ぜひご意見、ご感想をお聞かせください。
Eメール→info@kfaw.or.jp
Asian Breeze 100号(ウェブニュ-スレタ-)
フィリピンにおけるライスケ-キと女性の地位
-バトリシア・B・リクアナン(元フィリピン高等教育大臣)
ジェンダ-平等はSDGs達成の鍵
-織田 由紀子 (JAWW(日本女性監視機構)役員)
今回、節目となる100号は、国連第4回女性会議で「北京宣言と行動綱領」の交渉を主導して国連でも活躍され、フィリピンで長い期間に渡り、女性の高等教育に携われた、バトリシア・B・リクアナン元フィリピン高等教育大臣にフィリピンのジェンダ-問題を語っていただきました。またアジア女性交流・研究フォ-ラムで研究員を務められ、大学、NGOなどで、長年ジェンダ-問題に関わってこられた、織田由紀子さんに、SDGsの達成の鍵について解説いただいています。
100号 2024年1月発行
Asian Breeze 100号
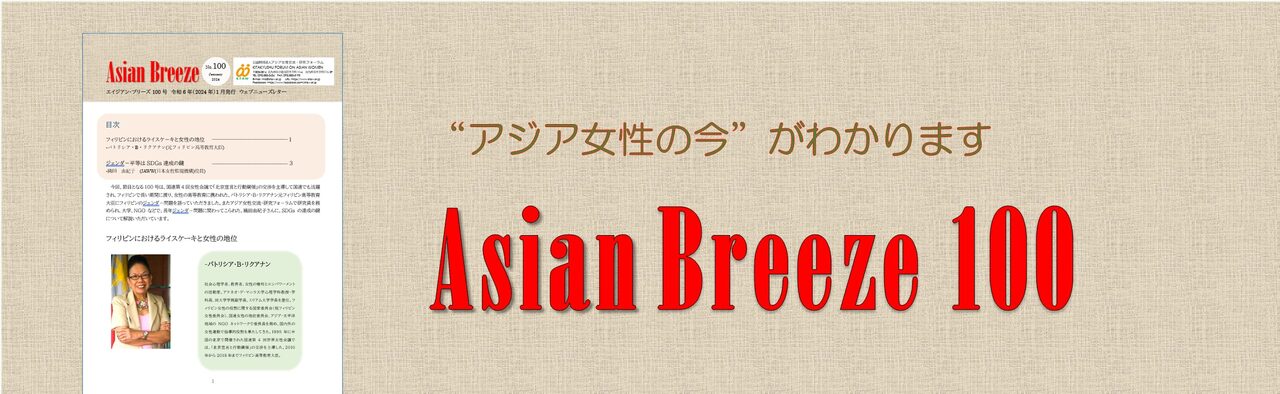
目次
- フィリピンにおけるライスケ-キと女性の地位
-バトリシア・B・リクアナン(元フィリピン高等教育大臣) - ジェンダ-平等はSDGs達成の鍵
-織田 由紀子(JAWW(日本女性監視機構)役員)
-織田 由紀子 (JAWW(日本女性監視機構)役員)
今回、節目となる100号は、国連第4回女性会議で「北京宣言と行動綱領」の交渉を主導して国連でも活躍され、フィリピンで長い期間に渡り、女性の高等教育に携われた、バトリシア・B・リクアナン元フィリピン高等教育大臣にフィリピンのジェンダ-問題を語っていただきました。またアジア女性交流・研究フォ-ラムで研究員を務められ、大学、NGOなどで、長年ジェンダ-問題に関わってこられた、織田由紀子さんに、SDGsの達成の鍵について解説いただいています。
フィリピンにおけるライスケーキと女性の地位

バトリシア・B・リクアナン
社会心理学者、教育者、女性の権利とエンパワーメントの活動家。アテネオ・デ・マニラ大学心理学科教授・学科長、同大学学務副学長、ミリアム大学学長を歴任。フィリピン女性の役割に関する国家委員会(現フィリピン女性委員会)、国連女性の地位委員会、アジア・太平洋地域のNGOネットワークで委員長を務め、国内外の女性運動で指導的役割を果たしてきた。1995年に中国の北京で開催された国連第4回世界女性会議では、「北京宣言と行動綱領」の交渉を主導した。2010年から2018年までフィリピン高等教育大臣。
フィリピンのジェンダー平等と女性のエンパワーメントには多くの要因があります。公式の政策は、女性と男性の平等を確認し、女性が国民生活において果たす重要な役割を認識しています。フィリピン憲法には明確なジェンダー平等規定があります。包括的な「女性と開発及び国家建設法」や、より最近の「女性のマグナカルタ」など、多くの重要かつ進歩的な法律があります。フィリピンは、アジアで初めて反セクシュアルハラスメント法を制定した国で、最近では「安全な空間法」に拡充されました。
コラソン・アキノ大統領の任期中に、初めてのフィリピン女性開発計画が立ち上げられ、その後もいくつかの後続計画が続きました。これらの国家計画の重要性は、フィリピン開発計画の一環として、女性、女性のイシュー(問題)、および女性の貢献を国家計画とプログラムすべての政府機関の業務の一部としていることです。女性のための政府の活動も、予算の5%をジェンダー平等と女性のエンパワーメントのプログラムに充てる「ジェンダー予算」(国立大学を含む、すべての政府機関の予算が対象)の創設により改善・向上しました。
国内政策に加えて、女性の権利に関する国際協定、例えば「女子差別撤廃条約」や「北京宣言及び北京行動綱領」なども重要な役割を果たしています。これらに署名したフィリピン政府だけでなく、4人のフィリピン女性が国連女性の地位委員会(UNCSW)の議長を務め、これらの画期的な文書の策定に大きく関与していたことに注目すべきです。
世界経済フォーラム「グローバルジェンダーギャップ指数」が2006年に発表されて以来、フィリピンは10年以上にわたり常にトップ10に入っていました。現在のフィリピンの順位は低くなりましたが、それでもトップ20に入っており、ここに入っている唯一のアジアの国です。そして、アメリカが初の女性副大統領を祝っている一方で、フィリピンは2人の女性副大統領と2人の女性大統領、さらに何人かの高い地位に就いている女性がいます。
ジェンダー平等と女性のエンパワーメントは、立法、政策及び指導力に加えて、草の根レベルで強力で活気に満ちた女性の運動、進歩的な法律と政策を推進し、サポートする女性NGO、そして重要な問題で自分たちの声を聞かせようとする女性NGOによって推進されています。
フィリピンにおける女性の地位は、女性運動が「ビビンカの原則」と呼ぶもので推進され、向上しています。ビビンカは国民的な美味であり、もち米の粉、卵、少しの砂糖から作られ、地元の白いチーズ、塩漬けのアヒルの卵、すりおろしたココナッツがトッピングされています。これを作るのは時間がかかるプロセスで、生地を丸い鍋に流し込み、その下に熱い炭を置き、さらに上にも熱い炭を置くというものです。実際、ビビンカは下からも上からも燃える炭で調理されています。そのため、女性の地位は上からの進歩的で啓蒙的な立法、政策、指導力による火と、下からの組織された、ダイナミックで勇敢なNGOによる火によって推進されています。
ですから、フィリピンの女性の地位には多くの事柄が働いています。しかし、問題もあります。女性は学校の入学、卒業の数で男性を上回っていますが、これらの成果が必ずしも良い仕事へのアクセスや仕事や昇進の機会での平等につながっているわけではありません。男性の平均賃金は都市部、農山漁村部ともに女性より高く、行政等の管理職、政治家としての地位に占める女性の割合は低いです。
否定的な態度やステレオタイプが社会に存在し、作用しています。これは、特に政治で顕著であり、根強い差別が作用しています。多くの人々が男性の方が優れた政治的リーダーであると信じています。そのため、女性は、選挙人の少なくとも半分を占めているにもかかわらず、候補者は少なく、深刻な状況が続いています。女性に対する暴力は様々な形で存在しており、これには、家庭内暴力、レイプ、セクシュアルハラスメント、トップの男性リーダーからの女性差別的な発言などが含まれます。
したがって、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための提唱と行動は続けられなければなりません。フィリピンの「グローバルジェンダーギャップ指数」の順位が低下した評価を分析し、是正する必要があります。「ビビンカの原則」は、より熱意と決意をもって適用されるべきです。
ジェンダー平等はSDGs達成の鍵

織田 由紀子
JAWW(日本女性監視機構)役員
これまで、(公財)アジア女性交流・研究フォーラム研究員のほか、大学教員、JICAプロジェクト専門家、委員会委員、NGO役員など、広く、研究、教育、開発実務、市民社会分野の活動に関わってきた。専門分野はジェンダーと持続可能な開発。SDGsに関しては、2012年の国連持続可能な開発会議(リオ+20)の誕生以降、2015年の「アジェンダ2030」の採択、その後日本での実施過程を、ジェンダーと市民社会の立場から関与してきた。近著は「環境・気候変動とジェンダー平等―どう相乗効果を生み出してきたか」『国際女性』No.36、2022年。
SDGサミット:2030年への折り返し
2023年9月18・19日、各国の首脳レベルが集まって国連SDGサミットが開催された。これは、2015年に国連で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」(以下SDGsと略)の実施状況に関する包括的なレビューを行い、実施を促進するためのもので、4年ごとに開催されている。2023年は、SDGs達成の目標年である2030年に向けての中間点にあたる。
SDGsの進捗状況については非常に厳しい見方が示されており、グテーレス国連事務総長はサミットの開会演説で「目標の15%しか達成できていない。誰一人置き去りにしないではなく、我々がSDGsを置き去りにしようとしている」*1と進捗の遅れに危機感を示した。これは、サミットに先立って国連が発表した「持続可能な開発報告2023(特別版)」で、「約束(SDGsの実施)は危機に瀕している」*2と警鐘をならしていたことを受けてのことである。同様に、毎年「持続可能な開発報告書」*3を発表している持続可能な開発ソリューションネットワーク(SDSN)でも、「このままのペースでは2030年までに達成できる目標は一つもない」と進捗の遅れを指摘している。*4
このような危機感に基づき、残りの7年間どうすればよいか、事務局長はまずSDGsの達成に向けての資金の確保をあげ*5、そのためには国際的な金融のアーキテクチャー(制度と流れ)の変革の必要性を強調した。さらに、取り組むべき分野として、食料、再生可能エネルギー、デジタル、教育、ディーセント・ワーク(人間らしい良質な仕事)と社会的保護、地球の危機の6つをあげ、ジェンダー平等はこれらすべての分野に関係する横断的視点であるとして、今こそSDGsの達成に向けての行動の時と鼓舞した*6。また、国連が指名した世界の15名の独立した科学者による「グローバル持続可能な開発報告書 (GSDR)」*7は、2030アジェンダのタイトルである「変革」を中心に*8、SDGsの実施促進こそゲームチェンジ、世界を変える機会とみている。
日本におけるSDGsの進捗と課題
日本では、企業、行政、市民社会を問わずSDGsバッジをつけている人が多く見られ、各メディアはSDGsを冠した番組や紙面を提供している。その結果、日本のSDGsの認知度は90%以上と驚くほど高い*9。しかし認知度の高さとは対照的に、各国のSDGsの達成状況を指数化した国別順位では、日本は2017年の11位から2023年には21位へと順位を下げている*10。中でも目標5ジェンダー平等は、進んでいない目標の筆頭格である。
日本ではSDGsは、総理大臣を長とするSDGs推進本部を中心に、「SDGs実施指針」(以下実施指針と略)に基づいて実施される。実施指針は、国連のSDGサミットに合わせて改定されることになっており、2023年11月に改定案が発表され*11、国民からの意見募集が行われた。12月には新しい実施指針が発表される予定である。指針に基づき毎年「SDGsアクションプラン」が作成され、それに沿って取組が行われるが、実態は各省庁の既存のプログラムを充当するものが多く、SDGsが掲げる目標を達成するためのプランとは言い難い。
進捗状況の検証は、国連で毎年開催されるハイレベル政治フォーラム(HLPF)で各国が報告する自発的国家レビュー(VNR)*12が最も包括的である。HLPFでの報告は毎年50カ国前後に限られるため、各国にとっては4~5年に一度となる。日本の直近の報告は2021年であった*13。進捗を測るためSDGsの169のターゲットに沿ってグローバル指標が定められており、これに対応する日本のデータは外務省のホームページから辿りつけるが*14、収集していないデータもあるため、国連等の報告書と比べての進捗比較や現状把握が難しい。日本におけるSDGsの進捗状況の検証の点では説明責任(アカウンタビリティ)に課題があるといえる。
ジェンダー平等の進展を測る―ジェンダー主流化と交差性(インターセクショナリティ)
国連ウィメンはSDGsの実施を通してのジェンダー平等の達成を検証するために、毎年『ジェンダースナップショット』(以下スナップショットと略) を発表している*15。スナップショットは2つの点で日本におけるSDGsおよびジェンダー平等の推進に参考になる。第1にSDGsの目標5ジェンダー平等だけでなく、17の全目標を通じて、ジェンダー平等の進展と課題を具体的に示していることである。これは「2030アジェンダ」の前文において、SDGsの17の目標の達成のためにはジェンダー視点の主流化が重要と謳われていることを形にしたものといえる。第2の特徴は、交差性(インターセクショナリティ)の視点を示していることである。スナップショット2023からいくつかの目標を例に紹介しよう。
SDGsの目標9「産業・技術革新」では、女性はSTEM(科学・技術・工学・数学)およびICT分野で働く人の4分の1であること、世界の特許保有者に占める女性の比率は17%にすぎないことなどの性別データを紹介している。さらに、女性は技術を利用した暴力 (technology-facilitated violence) にさらされる危険が大きいことに言及し、目標9「産業・技術革新」の達成のためには、科学技術やAI分野でのジェンダー障壁を取り除く必要性やジェンダーに基づく暴力への取組の重要性を示唆している。ジェンダーに基づく暴力は目標5や目標16「公正と平和」で言及されることが多いが、目標9の達成にとっても大切であることが分かる。加えて目標9では、AIによる顔や声の認証システムが、肌の色が白い男性に比べて色が濃い女性の認証に問題があるとの知見を紹介し、開発者の性別や人種の偏りがもたらす問題点を指摘し、多様な人が開発に参画する必要性に注意を喚起している。
目標11「持続可能なまちづくり」に関しては、2050年には世界の女性と少女の7割が都市に住みその3分の1はスラムなど不適切な居住環境に住むとの予測を紹介し、ジェンダー平等の視点から居住分野への公的投資の必要性を強調している。また、女性の障害者は女性全体の18%と推定されるが、各国の障害者に関する政策の中で女性の権利の保護と推進を掲げている国は27%(190カ国中52)に過ぎないとして、目標11の実施に当たり、障害のある女性の居住の権利保障を含めるべきことを示唆している。日本でもまちづくりに障害者の視点を含めている自治体は少なくないがジェンダーの視点を提起しているところはどのくらいあるのか、検証が必要である。
目標13気候変動に関しては、2050年までに気候変動のために1億6千万人の女性と少女が極度の貧困に陥り、2億4千万人の女性が食料不足になる危険があるとの性別データを示しているだけでなく、国連気候変動枠組み条約のパリ協定に基づいて各国が提出を義務付けられている自国の温室効果ガスの排出削減に関する報告書である国が決定する貢献(NDC)において、ジェンダー平等に言及しているのは55カ国、女性を変革の担い手と位置づけているのはわずか23カ国に過ぎないとのデータも紹介している。このように、目標13気候変動の達成には目標1の貧困課題と目標5ジェンダー平等が関係することを示している。
また、スナップショット2023は特に高齢者女性に焦点を当て、高齢者女性の貧困だけでなく高齢者女性に対する暴力の問題に注意を向けている。超高齢社会の日本こそ今後のSDGsの実施に高齢者女性の人権や尊厳の問題を主流化する必要があることを喚起してくれる。スナップショットでは、単に性別データだけでなく多様な人びとの多様な課題を示そうとしており、日本におけるSDGsの実施の検証の参考になる。
最後に、日本でSDGsの実施を通じてジェンダーに関する進展が見られたことを一つ紹介しよう。SDGsの各テーマに対する認知度*16および理解度*17調査によると、テーマの一つであるジェンダー平等についての認知度は90.2%で、食品ロスに続いて第2位、理解度に関しては食品ロス、再生可能エネルギーに続いて第3位(22.8%)であった*18。少なくともSDGsはジェンダーという言葉に対するアレルギーを取り除くのには貢献したと言える。
SDGs実施指針改定案でも認めているように*19、日本における目標5ジェンダー平等の遅れは明らかである。このことは、今後2030までの後半の7年間にジェンダー平等への取組を加速し成果を上げれば、困難な課題に取り組んだ国としてポストSDGsに向けて世界の動きをリードすることも可能であることを意味する。日本のSDGs達成の鍵は、ジェンダー平等への取組にあるといえる。
*2 https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/
*3 https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2023/
*4 https://www.sustainabledevelopment.report/news/press-release-sustainable-development-report-2023/
*5 開発途上国における資金不足に関しては2023年2月「SDGs達成のための刺激策」を発表。
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2023/02/SDG-Stimulus-to-Deliver-Agenda-2030.pdf
*7 https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/FINAL%20GSDR%202023-Digital%20-110923_1.pdf
*8 蟹江憲史「折り返し点を迎えるSDGs達成へ向けた課題」『国際秩序の危機―グローバル・ ガバナンスの再構築に向けた 日本外交への提言』、地球規模課題研究会報告書、日本国際問題研究所、2023 pp.57-66
https://www.jiia.or.jp/pdf/research/R04_Global_Issues/01-06.pdf
*9 電通、第6回「SDGsに関する生活者調査」
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2023/0512-010608.html
*10 SDGs市民社会ネットワークウエブ記事
https://www.sdgs-japan.net/single-post/sdsnreport2023
*11 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=350000208&Mode=0
*12 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/vnr/
*13 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/vnr/
*14 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/index.html
*16 「内容を詳しく説明できるくらい知っている」「簡単な内容なら説明できるくらい知っている」「説明できるほどではないが、一応内容まで知っている」「聞いたことがある程度」の合計
*17 「内容を詳しく説明できるくらい知っている」「簡単な内容なら説明できるくらい知っている」の合計
*18 https://www.dentsu.co.jp/news/release/2023/0512-010608.html
*19 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262018
今回のWeb版Asian Breezeはいかがでしたか。ぜひご意見、ご感想をお聞かせください。
Eメール→info@kfaw.or.jp
Asian Breeze 99号(ウェブニュ-スレタ-)
仁川デジタル性犯罪防止センターのワンストップ総合支援を中心とした
韓国におけるデジタル性犯罪の被害者支援
– キム ハンソル(仁川女性家族財団 IFWF)
GCFPの活動を通じた自己変革と地域住民への影響
– ソナム ドルジ(上級法務官 ゲレフ ソルムド行政区)
日常業務とその”発展”
– イェシェイ ラム(ブ-タン女性と子どもの国家委員会 副チ-フカウンセラ-)
ブ-タンの女性にかかわる困難な課題について
– ラデン ワンモ(CSO RENEWプロジェクトマネージャー)
*CSO (Civil Society Organization 市民社会組織)
I to T(Internet to Things あらゆるモノがインターネットに接続される。)が世界的な潮流となり、それに伴い、深刻なネット犯罪も多く発生していますが、近年韓国では、n番部屋事件などのデジタル性犯罪が大問題となっており、被害者保護について、北九州市の姉妹都市である韓国・仁川広域市から報告していただきました。 ブータンからは、JICAの研修で今年の5月から6月に来日された2名の行政官と、CSOの方に、日常業務に関連して、ジェンダー問題について語っていただきました。
99号 2023年12月発行